過去に産業革命を起こした技術に比べ、IT技術の発展スピードは速く、矢継ぎ早に革新的な技術が生まれている。これは、人智を超えたスピードであり、現代を生きる人間は、人類が過去に味わったことのない速度での成長を求められているのだ。まさに、未曾有の試練に見舞われているのである。

どういうこと?
僕たちが生きる現代は、昔、夢見ていた『21世紀』なのだ。遠い未来だった21世紀に僕たちは生きている。確かに、昭和の雰囲気が漂っていた21世紀の幕開けの2000年は、21世紀感は皆無であった。しかし、着実に技術は発展し、その発展スピードは、加速度的に上がっていたのである。ここまで発展し、広まったIT技術は、より速度をあげ発展してくだろう。そして、その技術を有効活用できる人間と、そうでない人間の格差を広げる。望む望まないは別として、僕たちが生きる現代は、未来社会における選別が始まってしまったのだ。
振り返ってみれば、1990年代後半から、緩やかに広がったインターネット。2000年代には、ほとんどの企業でパソコンの導入が進み、企業の業務はパソコンで行うことが当たり前になった。そして、2010年代からはスマートフォンが、僕たちの生活に革命的な変化をもたらしたのだ。現代は、知らない土地を歩くための地図も、知識欲を満たすための図鑑や辞典も、勇気が必要だったエロコンテンツも、スマホひとつで事足りるのである。

確かに・・・
一方で、「デジタル化なんて関係ない」「今まで通りで十分」と発展を拒む人間がいる。特に、昭和生まれの五〇代以上の世代に多いように思える。確かに、これまでの方法で何とかなることも多い。なので、昔ながらの方法で生活をするから、別に新しい技術なんて必要ないと考えてるようだ。でも、意固地になり、古い手法で何とか生活をするという状態は、周りの人間に多大な迷惑をかけているのだ。
例えば、スマホやパソコンの設定が分からず、子どもや若い同僚に頼んだり、オンラインサービスの使い方が分らず、家族に代行を依頼したり、一見、些細な負担だと思うかも知れないが、依頼された側は大きな迷惑と感じている。表面上は笑顔で対応してくれてはいるが、内心では「あ〜面倒くさい!! これくらい、自分でやりやがれっ!」と毒づいているのだ。

簡単にできるでしょ?
確かに、ひとつひとつの依頼は大したことがないかも知れない。でも、これから、どんどんと新しい技術生まれ、広まってくる。このような依存は、もっと増えてしまうのだ。大切なのでもう一度伝える。僕たちが生きているのは昭和時代ではない。21世紀という未来に生きているのである。環境は目まぐるしく変化している。環境の変化に対応できない生物が滅んでいく宿命なのは、過去の歴史を見れば明らかである。

くぅ、厳しい・・・
ここ最近では、人工知能(AI)の発展が著しい。ChatGPTに代表される生成AIの登場により、僕たちの働き方や生活は大きく変わろうとしている。これらの技術を理解し、活用できる人材は重宝され、そうでない人材は置き去りにされる可能性が高い。もちろん、職業によっては「AIなんて生活に関係ないから知らなくても問題ないし、大袈裟だな・・・」と思うかも知れない。でも、AIやロボットの技術に頼らなければならない未来は、遠くはない。
少子高齢化が進む日本では、将来的に、老人の介護はロボットに託されるだろう。その時に「機械が苦手だから」とか「ITってよく分からない」などとほざいていると、若者に迷惑をかけ、老害として煙たがられる悲しい未来しかないのだ。新しい技術を毛嫌いするのではなく、未来のため親しんでおく方が賢明だ。

そうかも知れないね・・・
そんな未来のために、何が出来るか。それは興味を持つことである。具体的には「スマホで何が出来るのか」「どうすれば良いのか」を知り、少しずつ触れる機会を増やし、慣れて行けば良い。初めは、何が出来るか、どうすれば良いのか、分からないことばかりで戸惑うかも知れない。でも、興味を持ち、試行錯誤することで徐々にスキルは上がる。何もしなければ、環境の変化に対応できず、滅ぶ未来しかないのだ。昭和生まれが得意の根性、忍耐、我慢で乗り切るしかない。
重要なのは、「できない」と諦めるのではなく、「まずは試してみる」という姿勢だ。誰もが最初は初心者である。年齢は関係ない。むしろ、昭和生まれは、豊富な人生経験を活かして、新しい技術の本質的な価値を理解できる立場にあるとも言える。
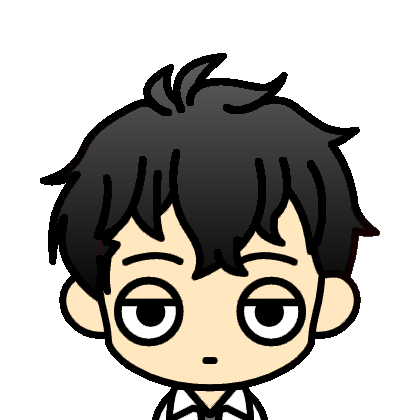
やるしかないんだ
デジタル社会への適応は、もはや選択肢ではなく必須となっている。しかし、これは危機であると同時にチャンスでもある。新しい技術を受け入れ、活用することで、より豊かで便利な生活を手に入れることができるはずだ。そして何より、自立した生活を維持し、次世代に負担をかけない未来を築くことができるのだ。
(了)

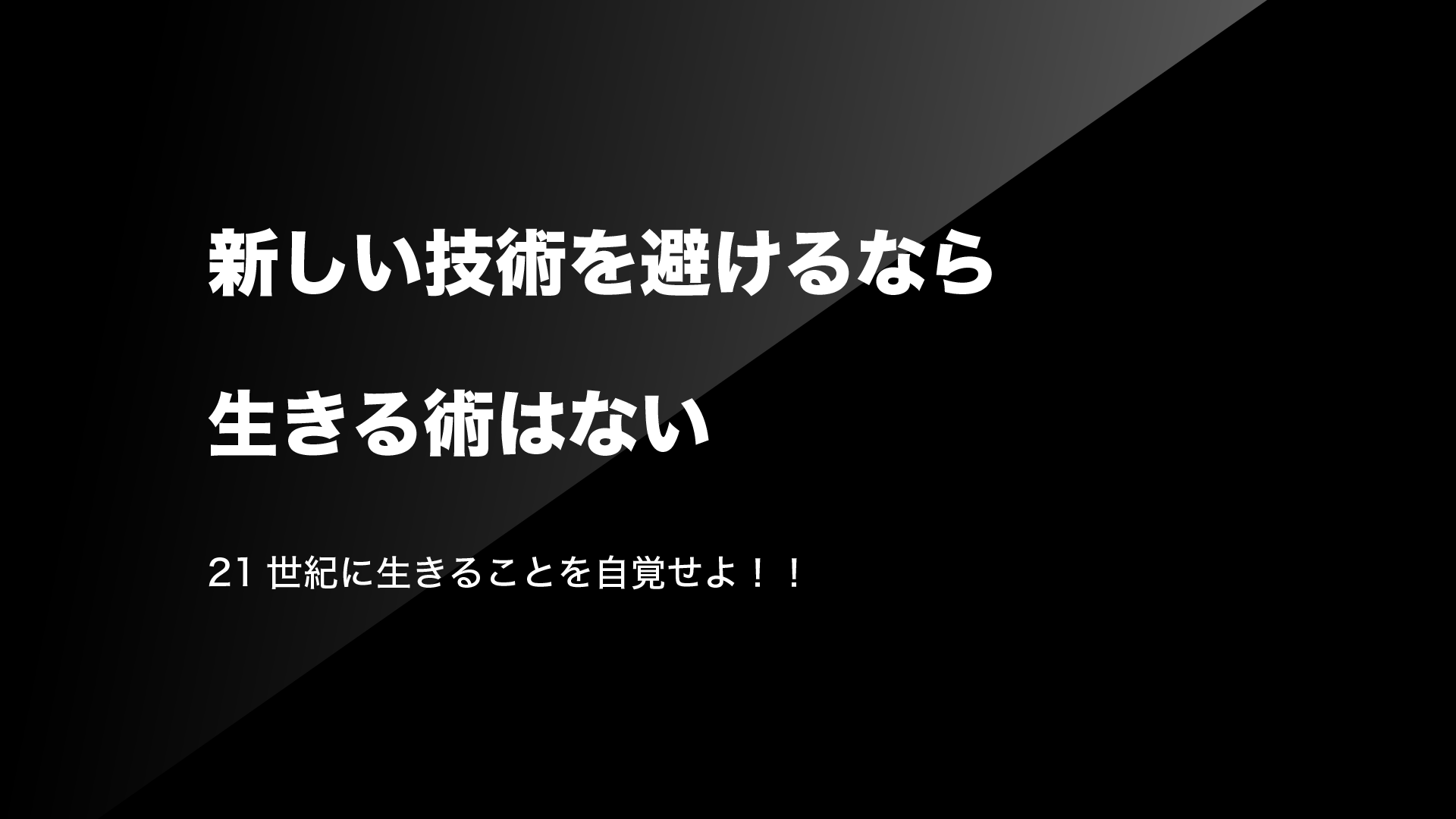

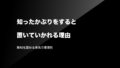
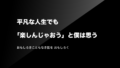
コメント