僕たちは、かつてないほど容易に情報にアクセスできる環境に身を置いている。現代社会は、インターネットという巨大な知の海に、誰もが自由に泳ぎ出すことができる時代だ。しかし、皮肉なことに、この情報過多の時代にあっても、組織における意思決定の質は必ずしも向上していないように見える。
その原因は、知識や経験が不足している者同士が集まって意思決定を行おうとするからである。もちろん、彼らは真摯な態度で議論に臨み、時には数時間、数日と膨大な時間を費やして結論を導き出そうとする。しかし、そこで生まれる結論の多くは、驚くほど稚拙で現実離れしたものとなってしまう。
なぜこのような事態が起こるのか。それは、彼らが「自分たちに何が分からないのか」という認識すら持ち合わせていない点にある。これは「無知の無知」と呼ばれる状態だ。自分たちの理解が及ばない領域の存在すら認識できないため、誰に相談すべきか、どこで適切な情報を得るべきかという判断もできない。結果として、表面的な理解や思い込みに基づいた議論が延々と続けられることになる。
さらに深刻なのは、このような状態に置かれた人たちは「物事の本質を見抜く力」が決定的に欠如していることだ。目の前の現象や問題に対して、なぜそれが起こっているのか、どのような要因が絡み合っているのかを分析する視点を持ち合わせていない。そのため、問題の本質から かけ離れた方向に議論が進んでいったとしても、誰一人としてそれに気付くことができない。
そして、いざ実行に移された決定が失敗に終わったとしても、そこから適切な教訓を引き出すことができない。なぜなら、失敗の真の原因を理解するための知識や分析力が欠如しているからだ。その結果、表面的な対処療法を繰り返すだけで、同じような失敗を何度も繰り返すことになる。にもかかわらず、彼らの自信は揺るがない。むしろ、議論を重ねた時間の長さや、その過程での真摯な態度が、その決定の正当性を裏付けているかのような錯覚に陥っている。
このような状況は、情報化が進んだ現代においても、驚くほど頻繁に目にする光景である。そして、こういった意思決定プロセスに関わることを余儀なくされる者にとって、それは耐え難い苦痛となる。なぜなら、明らかな誤りや無駄な回り道を目の当たりにしながら、その流れを変えることができないからだ。
しかし、この問題に対する解決策は、実は極めてシンプルである。それは、「正しい情報源にアクセスする能力」を組織として確立することだ。具体的には、どのような専門家に相談すべきか、どのようなデータベースや文献にアクセスすべきか、といった基本的な情報リテラシーを育むことである。
このような能力は、一見すると地味で基本的なものに思えるかもしれない。しかし、これこそが情報化社会における意思決定の質を決定づける重要な要素なのだ。いくら高度な情報システムが整備され、膨大なデータにアクセスできる環境が整っていても、それを適切に活用できる能力がなければ、すべては無意味となる。
今日の日本企業が直面している多くの問題は、実はこの点に起因している。組織における意思決定の質を高めるためには、まず「正しい情報にアクセスする能力」という基礎体力を養うことから始めなければならない。それなくして、真の意味での進化は望めないのである。
(了)

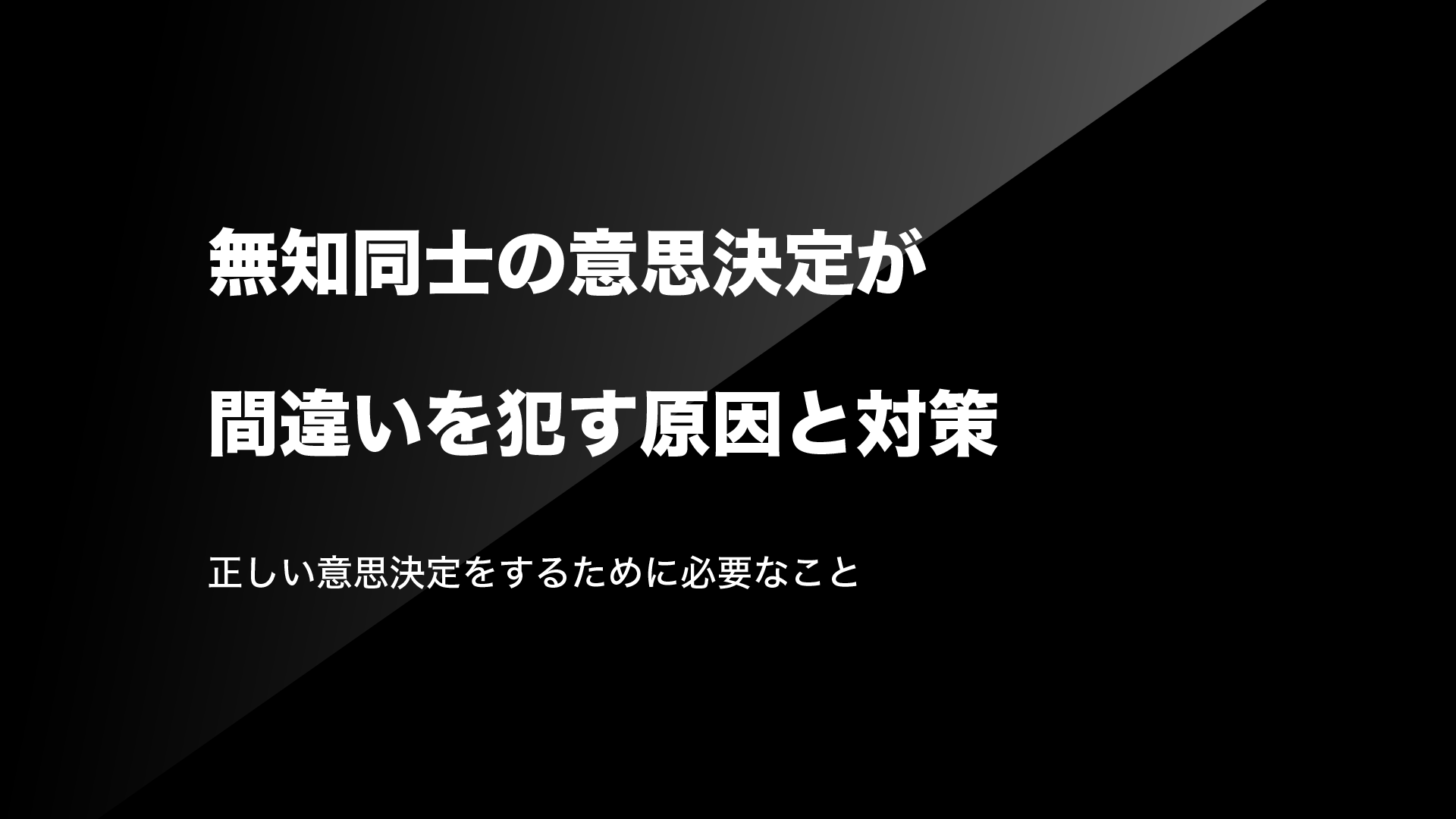
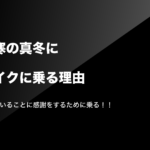
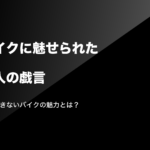
コメント