人間が集まり、組織を作ることは、古くから人類の生存戦略であり、また避けられない道でもあった。しかし、組織は生き物に似ており、その発展も衰退も、多くの場合、その中にいる人間の本質によって決まってくる。無知な者が周りに相談せず、思い込みだけで判断を下し、最終的に組織を崩壊させる・・・その過程をここに記そうと思う。
最初に指摘すべきは、無知な者たちが意思決定をする際の思い込みである。人間は、自分の無知を認めることを極端に嫌う生き物だ。無知であるがゆえに見誤り、表面的な知識だけで状況を判断し、あたかも正解であるかのように思い込む。相談を避けるのは、その思い込みが生む傲慢さ、あるいは無知を隠したい羞恥心からである。相談することで自分の無知が露わになることを恐れるため、彼らは思い込みに固執し、その場しのぎの結論を出してしまう。
ここで問題となるのは、無知な者が複数集まり、互いの判断を強化し合う現象である。これを同調という。同調は、時として組織に活力を与えるが、一方で間違った方向への暴走を引き起こす土台ともなる。無知な者同士が集まり、その判断を互いに認め合えば、それは疑いようのない確信となる。この確信が周囲の異論を遮断するようになると、彼らの中で小さな独裁が始まるのである。相談はますます避けられ、批判は理解不足として退けられ、やがては外部の意見さえ無視される。権威主義は、このようにして生まれる。
無知な者たちの決定が具体的な行動となって実行されると、その誤りは現場に影響を及ぼすようになる。最初は小さなゆがみであっても、誤った決定が重なるにつれて、次第に大きな亀裂となっていく。現場で働く者たちは、上層部の判断の誤りに気づきながらも、それを指摘することをためらう。なぜなら、指摘することで自分が反抗的な人間として扱われる可能性があるからだ。この沈黙が、無知な者たちの行動をさらに助長し、誤りが修正される機会を失わせる。こうして、間違った判断の積み重ねが組織全体に広がり、やる気は低下し、現場は疲弊していく。
この段階で外部の世界にも影響が出始める。組織の外では、無知な者たちの誤りはもはや隠しきれないものとなる。取引先や顧客、関係者たちは、組織の信頼性を疑問視し、距離を置き始める。評判は下がり、収益は減少し、かつて成功していた組織が徐々に立ち行かなくなっていく様子は、まるで風雨にさらされ、根が腐っていく木のようである。
組織崩壊の兆しが明らかになるとき、内部に残された者たちは三つの選択肢を迫られる。一つは組織にしがみつき、もはや避けられない崩壊を共に迎える道。二つ目は、組織を去り、新しい道を探す選択。そして三つ目は、最後のわずかな望みをかけ、無知な者たちを退け、改革を試みる道である。しかし、多くの場合、三つ目の選択がなされることは少ない。なぜなら、改革には時間と労力が必要であり、崩壊寸前の組織には、それを支える余力が残されていないからである。
結局、無知な者たちの行動がきっかけとなり、組織は自然消滅へと向かう。しかし、この過程で特に注目すべきは、無知そのものは必ずしも過ちではないという点である。無知は人間が本来持っている性質であり、これを完全に避けることはできない。問題なのは、自分の無知を自覚し、それを補うために他者と協力しようとする姿勢を持たないことである。相談を拒む態度、異なる意見を排除する文化、誤りを正そうとしない慢心・・・これらが組織崩壊を招く本質的な原因である。
人間社会において、無知が全くない世界は存在し得ない。重要なのは、その無知をいかに乗り越え、みんなの知恵として活かすかである。相談し、異なる意見を受け入れ、誤りを認めることができる組織こそが、困難を克服し、長く存続するのである。この教訓は、時代や地域を問わず、組織の歴史の中で繰り返し示されている。崩壊する組織の姿を目にするたびに、人は自分の無知と向き合い、相談することを怠らない決意を新たにするべきなのだ。


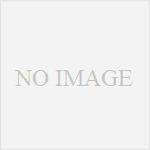
コメント