僕が思うに、頭が良い人間とアホな人間の決定的な差は、問題を解決する時のロジックというか、考え方というか、問題の原因の究明と対処法にあるような気がしてなりません。発生した問題の根本的な原因を潰すのか、その場しのぎで解決した感じになり、結局また同じ問題を繰り返すことになるのか。この差は実は想像以上に大きいんです。
例えば、会社でよくある「ミスが多い」という問題。アホな上司は「もっと気をつけろ!」「確認を徹底しろ!」と叫ぶだけなんです。でも、本来なら、なぜミスが起きるのか、どういう状況でミスが発生しやすいのか、そもそもそのプロセス自体に無理がないのか、もっと効率的な方法はないのかを徹底的に考えます。
我が社で、こんなことがありました。データ入力のミスが多いというので、部長が「三重チェックを徹底する!」と号令をかけたんです。確かにミスは減りました。でも、作業時間は3倍になり、社員の残業は増え、モチベーションは下がる一方でした。
そこに新しく来た課長が、全く違うアプローチを取りました。まず、どんなミスが多いのか詳細に分析したんです。すると、特定の時間帯や、特定のフォーマットでミスが集中していることが分かりました。原因を追究していくと、午後3時以降の集中力の低下や、紛らわしい入力フォーマットが問題だったんです。
その課長は、休憩時間の見直しとフォーマットの改善を提案しました。結果、チェック作業を減らしたにも関わらず、ミスは激減したんです。作業効率は上がり、残業も減り、社員の満足度も向上しました。
これって、まさに頭の良い人とアホな人の差を如実に表している例だと思うんです。アホな人は目の前の現象にだけ反応して、その場しのぎの対処をします。「ミスを減らすには確認を増やせばいい」という、子供でも思いつくような単純な発想しかできない。
一方、頭の良い人は、問題の本質を見抜こうとします。なぜそれが起きているのか、どうすれば根本的に解決できるのか、より良い方法はないのか—常に考え続けているんです。
この違いは、実は仕事に限らず、人生のあらゆる場面で現れます。例えば、子育て。「宿題をやらない」という問題に直面した時、アホな親は「やれ!」と怒鳴るか、「ご褒美をあげる」といった一時的な対処で終わらせようとします。
でも、本当に賢い親は違います。なぜ子供が宿題をやりたがらないのか、学校での様子はどうか、そもそも学習意欲を失っている原因は何か—じっくり観察し、考え、根本的な解決策を見出そうとするんです。
人間関係のトラブルでも同じです。「最近、友人と上手くいっていない」という状況で、アホな人は「もう付き合うのやめよう」とか「相手が悪い」で終わらせます。頭の良い人は、関係が悪化した経緯を振り返り、自分の言動を見直し、どうすれば関係を修復できるか真剣に考えます。
つまり、頭の良い人の特徴は、「表面的な対処で満足しない」「常により良い解決策を模索する」「長期的な視点で物事を考える」という点にあるんです。目の前の症状を一時的に抑えるのではなく、病気の原因そのものを治療しようとする、優秀な医者のような存在なんですよね。
これは決して、生まれつきの知能の差だけの問題ではありません。むしろ、物事に対する姿勢や、考え方のクセの問題です。だから、意識して習慣づければ、誰でもある程度は改善できるはずなんです。
例えば、問題に直面した時、まず「なぜ?」と考える習慣をつける。その「なぜ?」をさらに掘り下げていく。そして、複数の解決策を考え、それぞれのメリット・デメリットを比較検討する。こういった思考のプロセスを意識的に実践していけば、少しずつでも「頭の良い」問題解決ができるようになるはずです。
ただし、これには一つ重要な前提があります。それは「楽な方法を選ばない」という覚悟です。根本的な解決策を見つけ出すのは、往々にして面倒で時間のかかる作業です。その場しのぎの方が、短期的には楽に感じるかもしれません。でも、結局は同じ問題を何度も繰り返すことになり、長期的にはより大きな負担を強いられることになるんです。
要するに、頭の良さとは、問題解決に対する真摯な姿勢と、本質を見抜く洞察力、そして面倒なことから逃げない忍耐力の組み合わせなんだと思います。これは、努力次第で誰でも身につけられる能力なんです。
だから、「自分は頭が悪いから」と諦める必要はありません。むしろ、問題解決のアプローチを意識的に変えていくことで、誰でも「頭の良い人」に近づくことができるはずです。それが、僕の考える「頭の良さ」の本質なんです。
自戒を込めて。
(了)

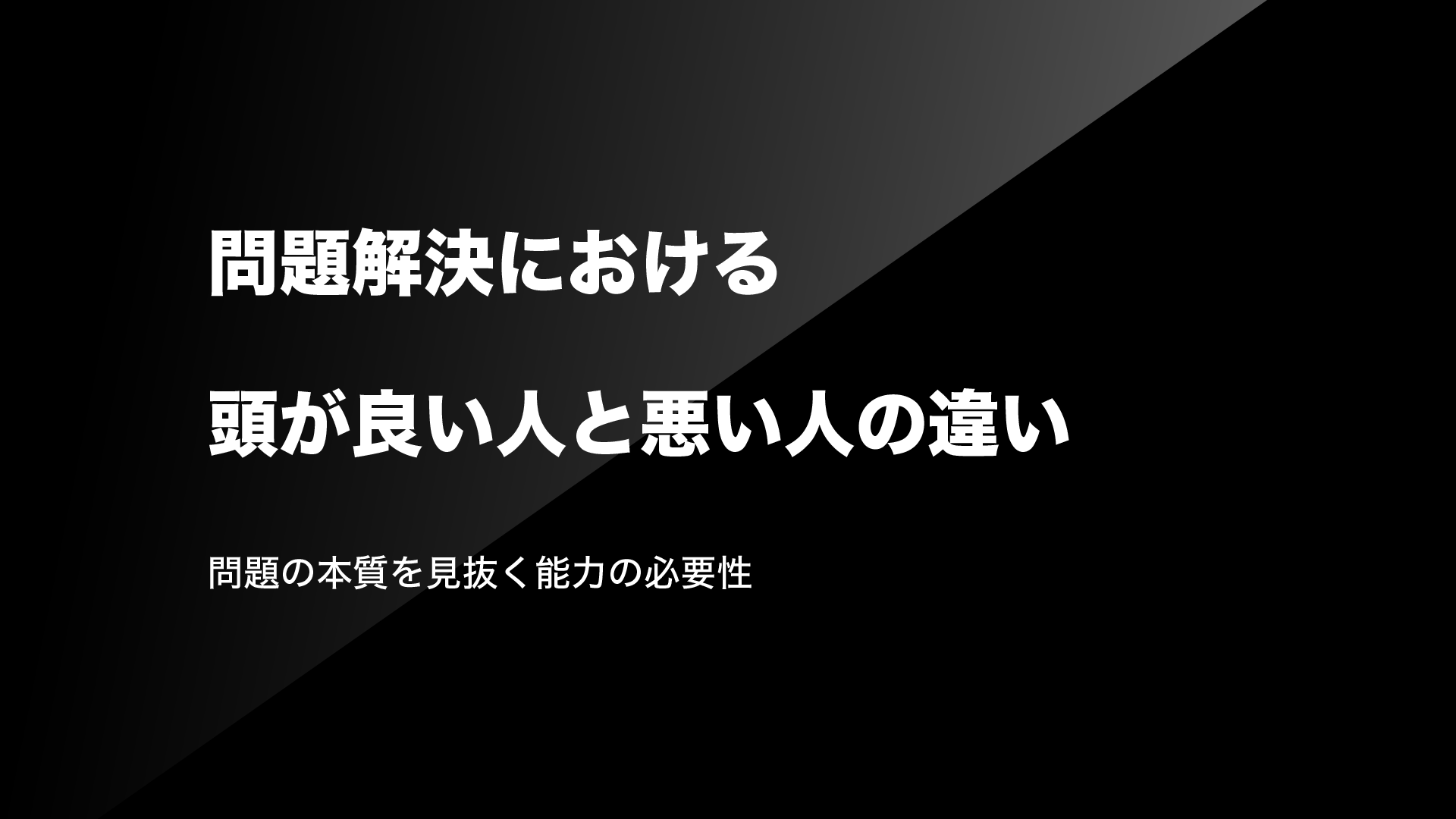
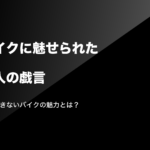
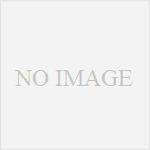
コメント