センスという言葉が嫌いである。僕からすると、センスという言葉は、無知な人間が多用する言葉である。巷で妬まれる程度のセンスは、努力して獲得できるスキルなのである。つまり、センスの有無は、学んだ質と量の違いである。もちろん、恵まれた才能の部分もあるが、それは、ごく一部の飛び抜けて特別な場合であり、一般社会にいる「センスがいい」と言われる人間は、過去に学び、スキルを獲得しているのである。デザインにしても、文章にしても、ファッションやメイクにしても・・・。
つまり、本人が意識したか、無意識かは別として、膨大な学習と経験、技術的な熟練で獲得したスキルをセンスという言葉で軽んじられるのは、些か不満なのである。僕は、web屋としてデザイン、ライティング、プログラミングを生業にしている。世間的に「センスが必要」とされる仕事である。だが、センスであるという言葉で片づけられたくない。
時として、僕自身も「センス」という言葉を使ってしまうことがある。特に、誰かに「どうやってそんなデザインを思いつくんですか?」と尋ねられたときなどである。その瞬間、これまでの数え切れない試行錯誤や、夜遅くまで、色々なデザインアイデアをかき集を眺めていた日々、競合サイトの分析に費やした時間について説明することが億劫に感じてしまう。そんなとき、つい「センスですかね」と言って誤魔化してしまう。
それは一種の防衛本能かもしれない。自分の弱さや不安、失敗の痕跡を他人に見せたくないという気持ちだ。完成品だけを見せて、その裏にある何百回もの試行錯誤は隠しておきたい。プロフェッショナルとして、常に完璧な仕事をしているように見せたいという虚栄心もあるのかもしれない。
しかし、この「センス」という言葉で片付けることは、結果として業界全体にとって害悪になっているのではないだろうか。若い人たちが「自分にはセンスがない」と諦めてしまうかもしれない。実際には、誰もが努力次第で習得できるスキルなのに、それを生まれつきの才能として神秘化してしまっている。
僕の経験では、良いデザインは必ず理由がある。色の組み合わせ、余白の取り方、フォントの選択、それぞれに明確な意図があり、そこに至るまでの思考プロセスがある。それは決して「なんとなく」ではない。ユーザビリティの理論、色彩心理学、タイポグラフィの基礎、そういった積み重ねの上に成り立っているのだ。
「センス」という言葉で片付けられることの多いファッションやメイクにしても同じことが言える。トレンドの把握、体型や顔型の分析、色彩の理論、これらを学び、実践を重ねることで、誰でも「センスのいい」着こなしやメイクができるようになる。それは才能ではなく、技術なのだ。
確かに、中には生まれつき優れた感性を持つ人もいるだろう。しかし、それはごく稀な例外であり、大多数の「センスのいい人」は、意識的にせよ無意識的にせよ、学びと実践を重ねてきた人たちなのだ。
僕が特に問題だと感じるのは、「センスがない」という言葉で、努力する前から諦めてしまう人たちの存在だ。彼らにとって「センス」は、自分には永遠に手の届かない何かとして認識されている。しかし、それは大きな誤解である。
むしろ、「センス」という言葉で片付けてしまうのは、本当の意味での努力ができない人たちなのかもしれない。地道な学習や、失敗を恐れない試行錯誤、そして何より自分の作品を客観的に分析する能力、これらを避けて通りたい人たちが、他人の成功を「センス」という言葉で片付けているのではないだろうか。
僕たちプロのデザイナーには、この誤解を解く責任がある。「センス」の裏にある努力や学びのプロセスを、もっと積極的に共有していくべきだ。失敗談も含めて、成功に至るまでの道のりを示すことで、「センス」という言葉の魔力を解き、誰もが成長できる可能性を示していく必要がある。
結局のところ、「センス」と呼ばれるものの大部分は、学べるスキルなのだ。それは決して生まれつきの才能ではなく、努力と時間をかければ、誰もが身につけることができるものである。この事実を広く伝えていくことこそ、クリエイティブな領域で活動する僕たちの使命なのかも知れません。
そのことに気づくのがセンスと言えば、センスなのだが・・・。
(了)


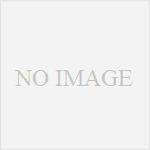
コメント