デザインという営みを、世間の人々は安易に「センス」という言葉で片付けてしまう。それは実に腹立たしいことだ。確かに、目の前に置かれた作品の良し悪しは、一目で判断できるかもしれない。ポスターやロゴを見て、人々は「この人はセンスがいい」と即座に評価する。だが、その軽率さこそが、デザインという深遠な技術を矮小化しているのだ。
世間の人々がデザインを「センス」と呼ぶのは、その成果物が視覚的な印象として瞬時に伝わってくるからだと思う。確かに、美しさや調和、心地よさといった要素は、感覚的なものだ。色使いの妙、形の美しさ、配置の巧みさ・・・これらは一瞬にして脳裏に焼き付く。しかし、それを「センスがいい」の一言で済ませてしまうのは、あまりにも短絡的ではないか。
実のところ、その背後には厳密な法則が存在する。デザインとは決して偶発的に生まれるものではない。そこには確固たる理論と技術が存在し、それらが複雑に絡み合って一つの作品を形作っているのだ。色彩理論、レイアウト、タイポグラフィ—・・・全てが科学なのである。そして、これらはすべて、学習と訓練によって獲得できる技術なのである。
デザインが「センス」として片付けられる背景には、もう一つの要因がある。それは、デザイナーの仕事の過程が外部からは見えにくいという事実だ。人々は完成品だけを目にする。しかし、その陰には幾度もの試行錯誤があり、理論に基づいた綿密な思考の積み重ねがある。それにもかかわらず、その努力の軌跡は完全に無視され、あたかも生まれながらの才能であるかのように語られる。これは実に遺憾なことである。
芸術の分野では、「天性の才能」という考えが根強く残っている。画家や作曲家の能力を、生まれつきの才能だと考える風潮が今なお存在するのだ。デザインもまた、この才能神話に囚われている。そのために、デザインは「センス」という言葉で片付けられ、その本質である技術的要素が軽視されてしまうのである。デザインは、アートとは一線を画す。画家や作曲家の能力はアートであり、デザインとは異なるのだ。
ここで強く主張しておきたい。デザインは決して天賦の才能ではない。それは学びと修練によって獲得される技術である。色彩理論、構図のバランス、視覚的調和・・・これらはすべて、理論に基づいて学ぶことができる。そして、その習得に才能は必要ない。必要なのは、ただ学ぶ意志と実践の積み重ねだけである。
例えば色彩理論を見てみよう。色には、それぞれに意味と効果がある。青色が信頼感を、赤色が情熱を、黄色が希望を表現するのは、偶然ではない。これらの特性を理解し、意図的に活用することで、効果的なデザインが可能になる。それは決して「センス」ではなく、明確な理論に基づいた技術なのである。
レイアウトについても同様だ。グリッドシステムという技術を用いれば、視覚的な秩序が生まれ、見る人の目線を自然に誘導することができる。要素同士のバランス、空白の取り方、これらはすべて計算された技術である。
タイポグラフィも重要な技術の一つだ。フォントの選択、行間の設定、文字間隔の調整——これらは、可読性と視覚的効果を高めるための具体的な技術である。それは決して感覚的なものではなく、明確な理論に基づいている。
これらの技術を習得すれば、誰でも優れたデザインを生み出すことができる。それは特別な才能を持つ者だけの特権ではない。必要なのは、理論の理解と実践の積み重ねだけである。「センスがいい」という安易な評価を超えて、その背後にある技術と理論を理解し、実践することこそが、真のデザインの習得につながるのだ。
デザインは確かに感覚的な魅力を持っている。しかし、その感覚を支えているのは、紛れもない技術なのである。デザインを学ぶということは、単なる感覚に頼るのではなく、理論的な枠組みを理解し、それを自分のものとして使いこなす力を養うことなのだ。そして、この技術は誰にでも開かれている。
デザインとはそういうモノである。


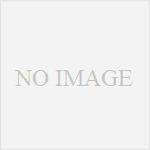
コメント